半導体工場(クリーンルーム)で歩留まりを下げる最大の問題のひとつが「微粒子ゴミ」。本記事では、初心者でもわかる言葉で、発生の仕組みから対策、そして現場で使える分離・除去の方法まで、実務の流れに沿ってまとめました。
- 本記事の要点
- 1. 半導体工場の「微粒子ゴミ」とは?
- 2. 微粒子ゴミがなぜ“問題”なのか?
- 3. 発生源を見える化する(層別:人・モノ・設備・空調)
- 4. 微粒子ゴミ対策方法
- 5. 分離・除去の仕組みと技術(基礎編)
- 6. 設備設計:空調・気流で分離する
- 7. 運用対策:人とモノの管理で“持ち込まない・舞い上げない”
- 8. 清掃・除塵の頻度と標準手順(SOP)
- 9. 現場での除去技術 選び方
- 10. 監視と可視化(“気づく”が遅れると全てが高くつく)
- 11. 微粒子ゴミ トラブル対応フローチャートの事例
- 12. 微粒子ゴミによる品質コストとROI(投資の考え方)
- 13. 工場クリーンルームの微粒子ゴミ対策・具体手順
- 14. 微粒子ゴミ対策 ケース別対策
- 15. 微粒子ゴミ対策 よくある質問(FAQ)
- 16. 微粒子ゴミ 用語ミニ辞典(初心者向け)
- 17. 微粒子ゴミ 関連記事
- 18. まとめ(今日からできる3つ)
本記事の要点
- 半導体工場における微粒子ゴミの正体と問題点が理解できる。
- 発生源を層別して、効果的な対策を選べる。
- 現場で実行できる分離・除去の方法(設備・運用・清掃・監視)の手順がわかる。
- すぐ使えるチェックリスト・標準手順・トラブル対応の型を持ち帰れる。
🧭 記事タイプ:ハウツー(問題 → 解決策 → 手順)
1. 半導体工場の「微粒子ゴミ」とは?
1-1. 定義とサイズ感
- 微粒子ゴミ(Particle, Dust):サブミクロン〜数十µmの固体粒子。露光・成膜・エッチング・洗浄・塗布現像など各工程で欠陥要因となる。
- クリティカル粒径:デバイス線幅や膜厚に対し、欠陥化しやすい粒径。例)線幅28nmなら、数十nm〜数百nmの粒子でも致命的。
- AMC(Airborne Molecular Contaminants):分子状のガス汚染(酸性・塩基性・有機など)。本稿の主役は固体粒子だが、実務ではAMC対策とセットで考える。
1-2. 粒子が引き起こす代表的な不具合
- レジスト欠陥:塗布ムラ、ピンホール、ブリッジ。
- 露光エラー:シャドー・欠像。
- 薄膜欠陥:パーティクル起点の突起、クラック、ピンホール。
- エッチング不均一:マスク残渣、オーバー/アンダーエッチ。
- 電気特性不良:ショート、リーク、早期故障(信頼性低下)。
💡 要点:粒子は「付く・運ばれる・発生する」の3経路でやってくる。源の抑制と拡散させない設計、付着したら迅速に除去が基本。
2. 微粒子ゴミがなぜ“問題”なのか?
- 歩留まり直撃:1枚のウェハに数個の粒子でも、回路密度が上がるほど致命率は上がる。
- 工程コスト増大:欠陥解析・リワーク・再処理・装置ダウンの連鎖。
- 品質・信頼性の悪化:微小欠陥は初期検査をすり抜け、フィールドで顕在化することも。
- 対策の遅れは高額化:設計段階での対策は安い。量産後の改造は高い。
👩🏫 先輩:「“空気がきれい”は出発点。どこで、どんな粒子が、どう付いたかまで分解するのが歩留まり改善の近道だよ」
3. 発生源を見える化する(層別:人・モノ・設備・空調)
3-1. 人(ヒューマンファクター)
- ガウン不備、肌・髪、動作の速さ、喋る・咳、紙粉、筆記具。
3-2. モノ(材料・消耗品)
- ウエハキャリア(FOUP/カセット)、トレー、包装材、ワイパー、手袋の摩耗粉。
3-3. 設備・ツール
- 真空ポンプの排気、搬送系の摩耗粉、ベアリング、Oリング、ベルト、ファン。
3-4. 建屋・空調(建材・床・壁・天井)
- 天井漏れ、床グレーチング摩耗、ダンパー、シール材、施工残渣。
3-5. 工程起因
- CMPスラリー、ドライエッチ残渣、灰化カーボン、レジスト粉化、蒸着スパッタのスパッタパーティクル。
✅ ポイント(層別の視点)
- 発生量(どれだけ出るか) 2) 付着確率(装置内の流れ・帯電) 3) 除去しやすさ(洗浄・ブローの効き)の3軸で優先度を付ける。
4. 微粒子ゴミ対策方法
A. 発生抑制(出さない) → B. 拡散防止・分離(運ばない) → C. 付着防止(くっつけない) → D. 除去(取る) → E. 監視(気づく)
- 設計:レイアウト、層流化、ULPA/HEPAフィルタ、ミニエンバイロメント、材料選定。
- 運用:入室手順、ガウン、動線、搬送ルール、ESD(静電気)管理。
- 清掃:ウェット&ドライ、ULPA対応掃除機、UPW(超純水)・IPA拭取り。
- 監視:パーティクルカウンタ、差圧・温湿度、AMCモニタ、表面汚染検査。
5. 分離・除去の仕組みと技術(基礎編)
5-1. 空気清浄(分離)
- HEPA/ULPAフィルタ:拡散・慣性・ふるい効果で粒子を捕集。装置上部のFFU(Fan Filter Unit)で天井から**一方向流(層流)**を作り、床のグレーチングへ還気。
- ミニエンバイロメント/SMIF/FOUP:ウェハを外気から隔離。局所のクラスを全室より厳しく保つ。
- 局所排気(LEVs):発塵源・薬液槽付近で吸引し、ダクトで安全に除去。
5-2. 付着防止(ESD・表面エネルギー)
- イオナイザで帯電中和。静電吸着による粒子付着を低減。
- 湿度管理:乾燥し過ぎると帯電が増える。プロセスと材料の許容範囲で最適化。
5-3. ウエハ/治具の除去(クリーニング)
- メガソニック洗浄(0.8〜2 MHz):微細粒子の剥離に有効。キャビテーションダメージが小さい。
- 超音波洗浄(20〜200 kHz):大型粒子・粒子層に有効だがデリケートな構造物への影響に注意。
- UPWリンス & スピンダライ:粒子を流して乾燥時のスポットを防ぐ。
- 化学洗浄:SC-1(アンモニア/過酸化水素/水)、SC-2(塩酸/過酸化水素/水)などで有機・金属の同時低減。
- ドライクリーン:CO₂スノー、プラズマ、ドライアイスブラスト等(対象により可否判断)。
⚠️ 注意:化学薬品は材料・膜との相性あり。金属腐食・表面荒れのリスクを事前評価(試験片・OOC評価)する。
6. 設備設計:空調・気流で分離する
6-1. クリーンルームの基本設計要素
- クリーンクラス(ISO 1〜9):装置上流ほど厳しく、下流へ流す。
- 風量設計:換気回数/hrや風速(例:0.25〜0.45 m/sの一方向流を目安)を工程に合わせる。
- 差圧管理:清浄側→汚れ側へ漏れない正圧階層。
- レイアウト:発塵工程を下流に、メンテスペースを分離、人の動線最短化。
6-2. FFU配置と床開口率
- 重要装置上部に高密度配置。床グレーチングの開口率とバランスを取り、短絡流や渦を作らない。
6-3. ミニエンバイロメント戦略
- FOUP+ロードポート+SMIFや、装置内の局所ISOクラスを厳格化。全室の要求を緩めても、実質的な粒子曝露を最小化できる。
🗂 設計のコツ:CFD(気流解析)で“死角”を潰す。設備搬入後はスモークテストで実流れを確認。
7. 運用対策:人とモノの管理で“持ち込まない・舞い上げない”
7-1. 入室手順(標準)
- 手洗い → 手袋一次装着 → エアシャワー。
- クリーンガウン(つなぎ・フード・マスク・ブーツ)を上流側で着装。
- 粘着ローラーで付着粒子を除去。
- 文具・紙類は最小化。必要ならクリーンペーパー。
7-2. 動作・所作
- 早歩き・大きな腕振りは再飛散の原因。ゆっくり・最短動線。
- 会話・咳・くしゃみは装置から離れて。
7-3. 物品・工具管理
- 搬入前に拭取り(IPA or UPW)。
- 低発塵の手袋・ワイパーを選定(繊維クズ注意)。
- 専用箱・抗静電袋で移送。
🧑🔧 新人:「“ゆっくり動く”だけでも粒子が減るんですね」
👩🏫 先輩:「うん。床上の粒子は人が起こす風で舞う。人は最大の発塵源だと覚えておこう」
8. 清掃・除塵の頻度と標準手順(SOP)
8-1. 頻度の決め方(目安)
- 毎日:装置周りの床・作業台、ロードポート、手が触れる箇所。
- 毎週:壁・天井周り、下回り、ケーブルダクト。
- 毎月:FFUプレフィルタ点検、床下スペース、工具棚の総点検。
- 工程イベント時:装置メンテ後、工事後、フォールト後は特別清掃。
8-2. 標準手順(例:装置周りのドライ→ウェット)
- ドライ:ULPA対応クリーン掃除機で上→下の順に吸引。
- ウェット:不織布ワイパー+UPWまたはIPAで“
一方向・一回拭き”。面を返しながら重複拭きしない。 - 仕上げ:イオナイザで帯電除去 → 乾燥確認。
- 記録:ロット番号・日時・担当者・使用薬品をログに残す。
📦 ボックス(NG例)
- 家庭用掃除機や市販モップを使う。
- 同じ面で往復拭き。
- ワイパーの“糸くず”放置。
8-3. 特殊清掃
- 装置内部の粉塵:真空チャンバは無水清掃を基本。手順書に従い、異物混入を避ける。
- CMPスラリー周り:乾燥固化前に即リンス。凝集前なら除去が容易。
9. 現場での除去技術 選び方
9-1. 乾式(ドライ)
- N₂ブロー:微粒子の吹き飛ばし。角で留まる粒子には斜め角度で。
- CO₂スノー:微粒子+有機残渣に有効。表面ダメージ少なめ。
- 粘着ローラー:ガウン・床用。繊維残りに注意。
9-2. 湿式(ウェット)
- UPW高流量リンス:粒子を“流す”。
- 化学洗浄(SC-1/SC-2/有機溶剤):粒子と有機・金属を同時に。
- メガソニック:ナノ粒子の剥離。空乏層ダメージ評価は事前に。
9-3. 物理吸着の解除
- イオナイザで帯電解除 → ブロー → 回収の三点セットにすると再付着が減る。
✅ 選定フローの例
- 基板:金属/酸化膜/レジスト有無を特定 → 2) 粒径と密度 → 3) 乾式/湿式 → 4) 条件最適化(温度・時間・流量・周波数)。
10. 監視と可視化(“気づく”が遅れると全てが高くつく)
10-1. 空中粒子
- ポータブル粒子計数器:装置上流・下流・作業点の定点測定。
- 定点モニタ:クラス変動のトレンドを監視。アラーム閾値を設定。
10-2. 表面粒子・フィルム汚染
- 表面汚染測定:拭取り法、光散乱式、落下菌(必要に応じ)。
- AMCモニタ:酸性/塩基性/有機の指標をロガーで把握。
10-3. KPIとダッシュボード
- DPW(Defects Per Wafer)、歩留まり、クリーンクラス逸脱回数、清掃完遂率。日次・週次で見える化。
🧩 原因切り分けの型
- 装置停止→改善:装置内発生源。
- 人が離れる→改善:ヒューマン起因。
- 風量上げる→悪化:渦・再飛散。
- イオナイザON→改善:帯電起因。
11. 微粒子ゴミ トラブル対応フローチャートの事例
- アラーム発報(定点モニタ/装置内センサ)
- 安全確認(薬液・ガス)→ 関係者招集
- 範囲特定:上流/下流、装置内/室内、時間帯。
- 発生源仮説:人・装置・空調・工程イベント。
- 一次対応:
- 風量・差圧の確認と暫定調整。
- 局所清掃(装置周辺→下流)。
- 入室制限・動線変更。
- 計測で検証:再発傾向・時間相関を確認。
- 恒久対策:部材交換、FFU増設、SOP改訂、教育。
- 再発防止レビュー:KPTで横展開。
12. 微粒子ゴミによる品質コストとROI(投資の考え方)
- 小さなSOP改善(教育・入室手順・清掃の質)→ 即効性・低コスト。
- 中規模(FFU増設、イオナイザ、搬送改善)→ 中コスト・中効果。
- 大規模(ミニエンバイロメント化、レイアウト刷新)→ 高コスト・高効果。
💰 判断軸:1個の粒子欠陥による歩留まり損失額 vs 対策投資。最も安いのは「発生を防ぐSOP」。
13. 工場クリーンルームの微粒子ゴミ対策・具体手順
クリーンルームの微粒子(ダスト)対策を、今日からできる最短手順で解説。工場現場の初心者でも安全・確実に運用できるゴミ対策の具体手順です。
手順(基本)
入室前準備:無発塵ウェア・手袋・マスクを正しく装着。ポケット内の紙・布繊維は持ち込まない。
エアシャワー:姿勢はV字で30秒、手は上げてゆっくり回転し全身に風を当てる。
入室動線:壁際を歩行し急な動作を避け、浮遊微粒子の再飛散を抑える。
拭き取り:上→下、清浄→汚染の順。無水アルコール+無発塵ワイパーを使用。
用具管理:モップ・ワイパーはエリア専用化。繊維落ちする雑巾・紙は使用禁止。
退出:工具・資材の拭き戻し、廃棄物は密閉袋で封緘。
よくあるミスと対策
・袖口/靴口の隙間→面ファスナー再調整。
・紙マニュアル持ち込み→ラミネート/クリーンノートに置換。
・消耗品の在庫切れ→棚ラベルで最小在庫と品番を明示。
14. 微粒子ゴミ対策 ケース別対策
ケースA:露光装置まわりで粒子が上がる
- 仮説:搬送の風、ガウンの擦れ、ロードポートの渦。
- 対策:入室人数制限、ロードポート正面の垂直層流強化、イオナイザON。
ケースB:CMP後の粒子欠陥が増える
- 仮説:スラリー乾燥・凝集、ブラシ摩耗。
- 対策:即リンス時間を延長、ブラシ交換周期短縮、スピンダライ条件見直し。
*CMPは半導体チップの表面をきれいに削って平らにするための研磨工程
ケースC:工事後にクリーンクラスが悪化
- 仮説:施工粉、シール不良、FFUプレフィルタ詰まり。
- 対策:特別清掃→プレフィルタ交換→スモークで渦確認→段階的に生産再開。
15. 微粒子ゴミ対策 よくある質問(FAQ)
Q1. HEPAとULPAの違いは?
A. ULPAはより微小粒子の捕集率が高い。ただし圧損が増え、風量や消費電力に影響。工程に応じて使い分け。
Q2. まず何から始めればよい?
A. SOP整備と教育、清掃の質を上げること。投資ゼロで効果が出やすい。
Q3. 露光・レジスト工程の要注意点は?
A. レジスト粉化、ベーク時の揮発、露光周りの層流乱れ。搬送・手動操作を最短・静かに。
Q4. 粒子カウンタの測定頻度は?
A. 立上げ直後・工事後は高頻度、その後はリスクベースで最適化。異常時は即時追加測定。
16. 微粒子ゴミ 用語ミニ辞典(初心者向け)
- 微粒子ゴミ:欠陥の原因となる固体粒子。
- HEPA/ULPA:高性能フィルタの種類。
- FFU:ファン付きフィルタユニット。天井に設置。
- 層流(Laminar Flow):一定方向に均一に流れる気流。
- FOUP/SMIF:ウエハを外気から守る容器/手法。
- UPW:Ultra Pure Water(超純水)。
- イオナイザ:静電気を中和する装置。
- AMC:空中分子状汚染。
17. 微粒子ゴミ 関連記事
- 製造現場の「微粒子ゴミ&異物」入門(初心者向け)
 製造現場の「微粒子ゴミ&異物」入門(初心者向け)製造現場の「微粒子ゴミ&異物」について初心者向けにわかりやすく解説しています。1. 微粒子ゴミ&異物とは(まず正体を掴む)製造品質や外観、衛生・信頼性を損なう恐れのある微小な固体粒子の総称。スケール感は1nm〜100µm、現場で厄介なのは5...
製造現場の「微粒子ゴミ&異物」入門(初心者向け)製造現場の「微粒子ゴミ&異物」について初心者向けにわかりやすく解説しています。1. 微粒子ゴミ&異物とは(まず正体を掴む)製造品質や外観、衛生・信頼性を損なう恐れのある微小な固体粒子の総称。スケール感は1nm〜100µm、現場で厄介なのは5... - 工場内の微粒子ゴミ&異物問題を徹底解説!
 工場内の微粒子ゴミ&異物問題を徹底解説!はじめに:なぜ「微粒子ゴミ&異物」が問題になるのか微粒子ゴミ(微小異物)は、製品の外観・寸法・機能・信頼性に影響を与える“見えにくい不良要因”です。特に5~50μmの粒子は、塗装のブツ、シール部のリーク、光学面の点欠陥、可動部のかじり、SM...
工場内の微粒子ゴミ&異物問題を徹底解説!はじめに:なぜ「微粒子ゴミ&異物」が問題になるのか微粒子ゴミ(微小異物)は、製品の外観・寸法・機能・信頼性に影響を与える“見えにくい不良要因”です。特に5~50μmの粒子は、塗装のブツ、シール部のリーク、光学面の点欠陥、可動部のかじり、SM... - クリーン化はここから始まる!基礎知識と技術の全て
 クリーン化はここから始まる!基礎知識と技術の全てこの記事は、微粒子ゴミ対策に関心を持つ製造業や医療業界の専門家、またはクリーンルームの管理者を対象にしています。微粒子ゴミがもたらす影響や、その対策に関する基礎知識を解説し、具体的な技術や方法を紹介します。これにより、読者が自らの業務に役立...
クリーン化はここから始まる!基礎知識と技術の全てこの記事は、微粒子ゴミ対策に関心を持つ製造業や医療業界の専門家、またはクリーンルームの管理者を対象にしています。微粒子ゴミがもたらす影響や、その対策に関する基礎知識を解説し、具体的な技術や方法を紹介します。これにより、読者が自らの業務に役立...
18. まとめ(今日からできる3つ)
- 入室SOPを見直す:ゆっくり動く/粘着ローラー徹底/ガウン点検。
- 清掃の質を上げる:一方向一回拭き+ULPA掃除機+ログ化。
- 監視を可視化:定点粒子データをダッシュボード化し、変化に即反応。
✅ 結論:微粒子ゴミの問題は“場当たり”では解決しません。発生抑制・分離・付着防止・除去・監視を手順化し、人・装置・空調を一体で最適化することが、半導体工場の対策の王道です。
おすすめBOOK:






































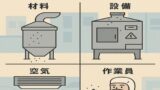

コメント