【初心者向け】微粒子ゴミ&異物対策の完全ガイド|洗浄・沈殿ろ過・シーリング・補助策まで徹底解説
製造現場の「微粒子ゴミ&異物」は目に見えないのに、歩留まり低下やクレームの主要因。本記事では初心者でもわかるように、洗浄/沈殿・ろ過/シーリング/その他の4分類で体系化。事例・チェックリスト・導入ロードマップまで総まとめ。
はじめに|なぜ今「微粒子ゴミ&異物対策」なのか
スマートフォン、EV、医療・食品、精密機械—あらゆる製品の品質は「微粒子の管理」に大きく左右されます。塵埃は人の髪の毛より遥かに小さく、目視では検知しづらい一方、塗装のピンホール、電子回路のリーク、軸受の早期摩耗、包装内異物によるクレームといった問題を引き起こします。対策は難しそうに見えますが、思想はシンプルです。①発生源を抑える、②混入経路を遮断する、③検出と除去を仕組み化する。本稿ではこの思想を「洗浄」「沈殿・ろ過」「シーリング」「その他(静電気・人・設備)」の4分類で整理し、現場でそのまま使えるレベルまで分解します。
微粒子ゴミ&異物の基礎知識
定義とサイズ感
一般に数μm以下の固体・液滴・繊維片などを「微粒子」と呼びます。0.3μmはHEPA性能評価の代表粒径、ULPAはさらに小さい粒子を対象とします。肉眼可視の目安は約50μm前後。つまり見えないレベルで管理するのが前提です。
品質影響の代表例
- 電子・半導体:パターン短絡、ワイヤボンド不良、接触抵抗増。
- 精密機械:摺動部摩耗、シール劣化、異音。
- 医薬・食品:異物混入、回収(リコール)リスク増。
- 塗装・表面処理:ピンホール、ブツ、密着不良。
発生源と混入経路のフレーム
発生源は「人・設備・材料・環境・工程外(搬送/保管)」に大別できます。混入経路は主に空気(浮遊/落下)・液体(洗浄/薬液/冷却水)・接触(手袋/治具/梱包)。まずは現場の流れ図に“発生→輸送→付着”を描き込み、どこで制御するかを見極めます。
測定とKPIの基本
- 空中粒子:パーティクルカウンタでクラス管理、差圧と換気回数。
- 表面清浄:テープリフト/顕微観察、拭取りカウント、白布試験。
- 液中粒子:液体パーティクルカウンタ、ろ過後重量差。
- KPI:不良率(異物起因)、清掃完遂率、フィルタ差圧、静電電位、入室遵守率。
4分類の全体像と優先順位
対策はバラバラに導入すると費用対効果が落ちます。おすすめは「シーリング→ろ過→洗浄→その他」の順で「環境→工程→人・設備」の階層に沿って設計し、最後に静電気や教育で微粒子の“引き寄せ”と“ばら撒き”を抑える方法です。
分類①:洗浄による微粒子ゴミ対策
「付着した粒子を落とす」王道のアプローチ。成功の鍵は①前処理→②主洗浄→③リンス→④乾燥の一連を“再付着させない流路”で構成することです。
水洗浄(アルカリ/中性/酸)
- 長所:安全・低コスト・設備が汎用。
- 短所:油脂・レジストには限界、乾燥でウォータースポット。
- 要点:温度・pH・界面活性剤の選定、処理時間。逆流リンスで清浄度を段階的に上げます。
溶剤洗浄(IPA・炭化水素・フッ素系等)
- 長所:油分と粒子を同時に除去、乾燥が速い。
- 短所:安全衛生・環境規制・コスト、引火性対策。
- 要点:密閉型/蒸気洗浄、回収再生。作業者教育と換気・防爆。
超音波/メガソニック洗浄
キャビテーションで微細溝の粒子を剥離。周波数が低いほど衝撃は強く、高いほど穏やかで微細粒子に効きます。ワーク材質・表面粗さ・接合部を考慮し、出力/時間を詰めます。
ドライ洗浄(CO₂ドライアイス、プラズマ、UV-O₃)
水や溶剤を避けたい場合の選択肢。切粉・有機汚染膜の分解/飛散抑制に有効。治工具や光学表面などで採用例が増えています。
乾燥:再付着を防ぐ設計
- 温風/遠赤:シンプル。粉塵混入を避けるためHEPA吹き出し推奨。
- 真空乾燥:低温で溶剤・水分を除去。
- IPA置換・マランゴニ:ウォータースポット抑制、歩留まり安定。
- N₂ブロー:酸化/粉塵低減。ノズルの清浄維持がカギ。
洗浄SOPチェックリスト
- 入出庫トレーは清浄区と準清浄区で分色運用。接触面は毎ロット拭取り。
- バス更新は導電率・濁度・有効成分濃度に基づく基準管理。
- 逆流リンスの流路図を掲示し、弁位置のヒューマンエラーを防止。
- 乾燥炉入口にエアシャワーミニブースを設置、搬送中の落下塵を遮断。
分類②:沈殿・ろ過による微粒子ゴミ対策
「環境から粒子を分離し、そもそも付着させない」アプローチ。空気・液体の双方でのフィルタ設計と保全が肝です。
沈殿/凝集(液系)
- 重力沈降:簡便・低コスト。清掃保全の徹底が必須。
- 凝集沈殿:粒子をフロック化して沈降促進。pH/薬剤量の管理が歩留まりを左右。
液体ろ過(バッグ/カートリッジ/メンブレン)
| 方式 | 特長 | 代表用途 | 管理指標 |
|---|---|---|---|
| バッグ | 大流量・荒取り | 前処理 | 差圧/交換サイクル |
| カートリッジ | 汎用・段階細化 | プロセス | β値/差圧 |
| メンブレン | 最終精密ろ過 | 充填前 | 孔径/泡点 |
空気ろ過(HEPA/ULPA/プレフィルタ)
- 段階ろ過:プレ→中性能→HEPA/ULPA。前段で粉塵負荷を削減し寿命延長。
- 差圧監視:交換の客観基準。閾値超で警報。
- 吹出し設計:層流/乱流の使い分け、死角を作らない機器配置。
サイクロン/遠心分離
粉体や切削ミストの一次捕集に有効。集塵機前段でフィルタ負荷を下げ、爆発性粉じんの安全対策にも寄与します。
保全・点検の型
- フィルタは型式×孔径×装着位置を台帳化。ロットトレーサビリティを付与。
- 差圧・風速・換気回数は月次点検、季節変動時は増頻。
- 沈殿槽は汚泥量×清掃履歴を見える化、堆積→再飛散を防止。
分類③:シーリング(密閉・遮断)による微粒子ゴミ対策
外部から「入れない」、内部で「舞い上げない」。環境設計の主役です。
クリーンルーム設計の要点
- 清浄度:目標製品に応じたクラス設定。過剰スペックを避けて局所クリーンも併用。
- 気流:層流は重要工程へ。リターン位置と人の動線で巻き上げを抑制。
- 陽圧・差圧:汚染区→清浄区への逆流を防ぐ。差圧は常時モニタ。
- ゾーニング:更衣→前室→準清浄→清浄。搬入物も同様に段階化。
関連記事:クリーン化はここから始まる!基礎知識と技術の全て

局所シーリング(ミニエンバイロメント/アイソレータ)
設備全体ではなく「工程の核心」をシールド。投資を抑えつつ効果を集中させます。樹脂成形の取り出し、粉体計量、露光・貼合などで有効。
パッキン・Oリング・シール材の選定
- 摩耗粉が出にくい材質(FKM、EPDM、PTFE等)を条件に合わせて選定。
- 表面粗さと取付溝寸法を図番管理、交換周期を「時間×回数」で定量化。
- グリースは低揮発タイプ、塗布量の標準化でミストと粉塵を抑制。
人と物流のシーリング
- 入室教育:手洗い→コロコロ→更衣→エアシャワー→入室の順を掲示。
- 台車・パレットは清浄区専用化。輪止めやタイヤ清拭で持ち込み塵を遮断。
- 梱包材の開封は準清浄区で実施。内袋を清浄区に持ち込む。
分類④:その他の微粒子ゴミ対策(静電気・人・設備・清掃)
静電気対策
- イオナイザ(バー/ブロー/スポット)で帯電を中和。風量は「除電効率×再付着」のバランス。
- 床・マット・治具は帯電防止、導通確認を定期点検。
- 作業手順に「接地確認→除電→作業→保管」を組み込む。
関連記事:初心者のために静電気の基礎知識と対策をわかりやすく解説【図解】
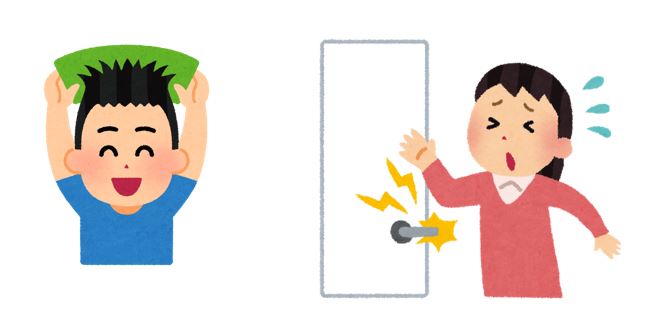
作業者管理と教育
- クリーンウェアは着衣順序・サイズ適合が最重要。袖口・足首の密閉性をチェック。
- 手袋は作業内容で使い分け、開封→装着→交換のロット管理。
- 入室遵守率、溶剤取扱い、拭取り圧・回数などを映像で標準化。
設備摩耗と潤滑管理
- 摩耗源(コンベヤ、ギヤ、ベルト、研削粉)の特定と囲い込み。
- 潤滑剤の飛散を抑えるノズル、ミストコレクタ、ドレン管理。
- 予防保全の周期は稼働時間×環境粉塵量で見直し。
材料の前処理・保管
- 原料受入時にふるい/磁選/ブロワで荒取り。袋外面の拭取りで持ち込み塵を削減。
- 保管棚は密閉型、開封口にキャップ。先入先出(FIFO)で長期保管の劣化粉を防止。
清掃設計(掃除で撒き散らさない)
- 「上→下」「乾式→湿式」の順で実施。モップ繊維の脱落対策。
- 掃除機はHEPA排気。紙モップ/ワイパーはロット表示で交換周期を可視化。
可視化・IoT・データ活用
- 重要工程に粒子カウンタ・差圧・静電電位を設置し、SPC管理図で傾向監視。
- 異常時はなぜなぜ5回+写真・動画で原因を追跡。是正後は再発防止策を横展開。
微粒子ゴミ&異物管理 改善事例
事例1:電子実装のブツ不良を30%削減
貼合前のスポットイオナイザ+N₂ブロー、乾燥炉入口の局所層流フード追加、トレーの拭取りSOP化で歩留まり改善。効果の7割は“入れない”と“帯電させない”。
事例2:樹脂成形の黒点(カーボン)低減
ホッパ乾燥機のフィルタ段階化とパージSOP、金型周辺のミニエンバイロメント化、材料袋の準清浄区開封で顕著に低減。
事例3:食品充填の異物クレームゼロ化
資材の開封区分け、エアシャワー更新、ライン停止時のカバー装着を標準化。清掃順序の逆転(乾→湿)を是正して撹拌粉塵を抑制。
費用対効果(ROI)の考え方
典型式:ROI(%) = (削減不良損失 + 削減清掃/保全工数 + 回収リスク回避額 - 導入/運用費) ÷ 導入/運用費 × 100
小さく始め、局所シーリング+段階ろ過+除電の三点セットから試すと投資対効果が出やすい。
導入ロードマップ(90日プラン)
- 0〜2週:現状診断(発生源マッピング、計測、動画観察)、暫定対策(清掃順序是正、除電ブラシ)。
- 3〜6週:試作対策(ミニフード、段階ろ過、洗浄条件DoE)。効果測定。
- 7〜10週:設備・SOP本実装、部材トレーサビリティ整備。
- 11〜13週:監査・教育・KPI運用、横展開。
トラブルシューティング早見表
| 症状 | 主因候補 | 即効策 | 恒久策 |
|---|---|---|---|
| 乾燥後の白跡 | 水質/乾燥条件 | 純水リンス追加 | IPA置換・マランゴニ導入 |
| 貼合時のブツ | 帯電・搬送風 | スポット除電+N₂ブロー | 局所層流・動線見直し |
| ろ過差圧急上昇 | 負荷過多/薬液変質 | 前段フィルタ追加 | 多段化と交換基準の数値化 |
| 清掃直後に粉塵増 | 清掃順序ミス | 湿式で仕上げ | SOP・教育動画化 |
キーワードと内部リンク案(編集時に差し替え推奨)
まとめ|4分類を「組み合わせ」で回す
本稿の要点は次の通りです。
- 洗浄:前処理〜乾燥まで“再付着させない”流路で設計。
- 沈殿・ろ過:段階化と差圧モニタで性能維持。
- シーリング:ゾーニングと局所クリーンで“入れない”。
- その他:静電気・人・設備・清掃を型化して“ばら撒かない”。
まずは現状診断→局所シーリング+段階ろ過+除電から着手し、効果を測定しつつ洗浄条件を最適化。KPIで運用を回せば、歩留まりとクレームは着実に下がります。
微粒子ゴミ&異物管理 よくある質問(FAQ)
Q. まず一番コスパが良いのは?
A. 局所シーリング(ミニフード)+プレ/HEPAの段階ろ過+スポット除電の三点セット。小投資で効果が見えやすいです。
Q. クリーンルームなしでどこまで行けますか?
A. 多くの一般工場は局所クリーンで十分な場合が多いです。人・物流の分離と清掃順序を徹底すれば、体感以上に改善します。
Q. 洗浄液はどれを選ぶべき?
A. 汚染の性状(粒子/油/有機膜)と材質(腐食/膨潤)で選定。安全・環境制約と乾燥方法も同時に設計しましょう。
Q. フィルタ交換の基準は?
A. 差圧×使用時間×処理流量で数値化。運用は「最大差圧の◯%」などのルール化が便利です。
Q. 静電気対策が効かない時は?
A. 接地の導通不良、風量不足、ノズルとワーク距離の不適合が典型。電位測定→対策点検→再測定の順で絞り込みます。
SEO向けキーワード候補
#微粒子ゴミ対策
#クリーンルーム 微粒子
#洗浄 沈殿 ろ過 シーリング
#工場 異物混入 防止
#初心者向け 品質管理
おすすめBOOK:
























コメント